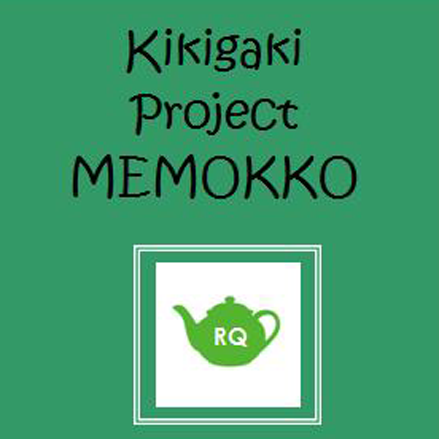| 文字サイズ |
普及していたお風呂
お風呂はどこの家にもありましたね。
まあるいドラム缶のような大きいの、1個半くらいの長さにしてね、丸い筒があって、そこで木なんか焚いてそして沸かしたの。あとは松から下りる松笠(まつぼっくり)ありますよね。あれ拾ってきて。あれは燃すのに最高、良かった。拾うのは、子どもばかりでなく大人もついて行くからね。半造なんて、危険だからね。笹浜の家は10人家族だったから、家族だけでお風呂に入っていました。
小鯖に嫁に来てからね、この辺は、どこの家にも風呂があったけど、それでもね、「もらい湯」はさせてたの。お風呂があっても、燃料の木の蓄えが無かったりすれば、「貰いにいってくるか」っていうわけでみんな寄ってくるわけさ。40年前まで住んでた家は坂の一番下にあったんだけど、周りはみんなね、お風呂に入るように呼びにいったの。お姑さんから「どこそれ、来ないから行って呼んで来い」って呼びに歩かせられたの。井戸は家のそばだから、中のお湯が少なくなれば水を汲みに行って足して。ぬるくなれば、立って行って、風呂の火を燃して。そして、「もうそろそろ、みんなお風呂から上がって家に帰ったから、あんたも入って寝らい(寝なさい)」って言われるわけ。
鉄砲風呂
家は金はなかったけれど、借金もありませんでした。昔はそんなにお金はいらなかったんです。食べ物が手に入りさえすれば、あとはとにかく、薪があれば正月が越せたんです。薪は山から採って来る、米は作ってる、野菜も作ってる、おかずは海で獲れる。電気料はその頃もあったけど、プロパンガスでなく、かまどもお風呂も薪でした。
そのころのお風呂は、鉄砲風呂でした。水だって、井戸から汲んで沸かすから一仕事なんですよ。入り終わると今度は、風呂桶を乾かすわけです。乾かすのに横にして、また風呂を沸かすときに立てる。だから、「風呂を立てる」って昔は言うわけなんです。風呂を今晩立てろ、っていうのは風呂は横にして乾かしてるから、それから来ているんでしょう。
昔はお風呂は、3軒の家で1軒あるかないかでしたから、当時は「もらい風呂」って言う風習がありました。「隣の父ちゃん、今晩風呂もらいにくるから」などという会話があったんです、あの時代は。
Navigation
Please use the navigation to move within this section.